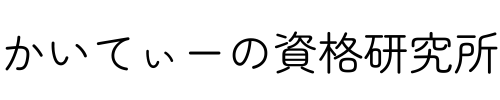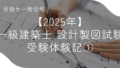みなさん、こんにちは。
こちらでは、2021年度に建築設備士試験に合格した管理人かいてぃーが、当時の勉強方法などを記載します。
私にしては珍しくストレート合格することができましたが、仕事と勉強を両立するのはとても大変かと思います。
働きながら効率よく勉強するコツなど参考にしていただけたら嬉しいです。
2025年 建築設備士試験日程
学科試験:2025年6月22日(日)
設計製図試験:2025年8月24日(日)
最新の情報については、建築技術教育普及センターのHPをご確認ください。
管理人かいてぃーが建築設備士を受験したときの保有資格
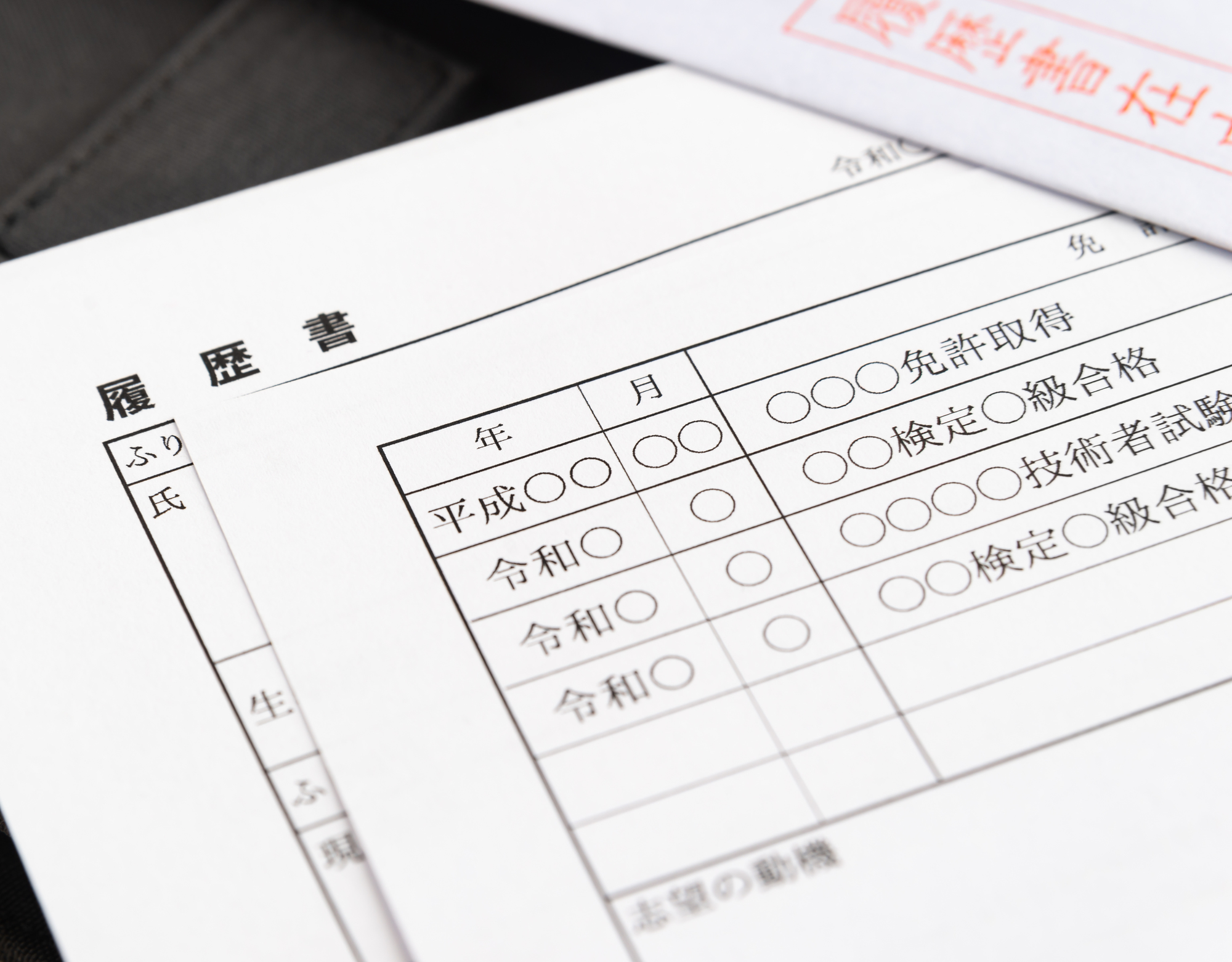
- 1級管工事施工管理技士
- 2級管工事施工管理技士
- 2級電気工事施工管理技士
- 2級建築施工管理技士
- 消防設備士甲種4類
建築設備士を受験しようと思ったきっかけ
建築設備の知識をもっと深めたいと思った
1級管工事施工管理技士の資格を取得したことを機に、建築設備の知識をさらに深めたいと思うようになりました。
学科試験と設計製図試験で構成される建築設備士試験は、設計系の知識を問われる試験です。
私は図面を描くことは得意ではありませんでしたが、建築設備士の試験は設計の知識を身につける良い機会だと思えました。
二級建築士に合格できなかった悔しさを晴らしたい
2017年と2018年に二級建築士に挑戦しましたが、設計製図の壁を越えられずに悔しい思いをしました。
建築の道で諦めたくないと、別の角度から挑戦しようと決意。
そこで出会ったのが、建築設備士という資格でした。
設計製図のスキルアップはもちろん、得意分野である建築設備の知識を深めたいと改めて思うようなりました。
そして、2021年に建築設備士の受験を決意しました。
建築設備士の勉強方法
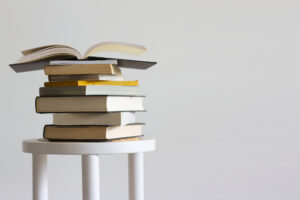 私は、総合資格学院の独学支援講座という講座で勉強することにしました。
私は、総合資格学院の独学支援講座という講座で勉強することにしました。
この講座は、設計製図対策のみの金額で学科試験の過去問が配布され、学科試験合格後は設計製図試験対策の映像講義を受講するという内容です。
また、設計製図対策として、建築設備技術者協会が講習会で使用するテキストを使用しました。
総合資格学院を選んだ理由
学科試験対策
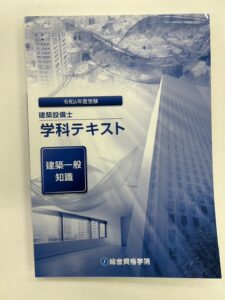

過去問題集が10年分収録されている
市販の過去問題集の収録年が5年分であるのに対して、総合資格学院は10年分と多くの過去問題に取り組めることが魅力だと感じました。
日建学院の建築設備士講座は市販の過去問題集を用いて行うため、せっかく講座を受講するなら市販されていない過去問題集を使いたいと思ったのも総合資格学院を選んだきっかけです。
過去問題集が科目ごとに分かれている
学科試験は、「建築一般知識」、「法規」、「建築設備」の3科目で構成されています。
市販の過去問題集だと1冊で3科目分の過去問題が記載されていますが、総合資格学院の過去問題集は、科目ごとに分冊されているため、科目ごとで勉強しやすいのが魅力だと感じました。
設計製図試験対策
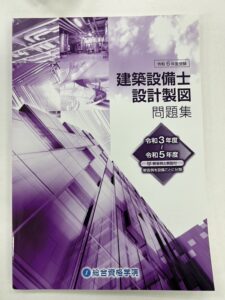
オリジナル課題が豊富
その年度の課題に沿ったオリジナル課題を10個近く解きます。
講習日に1課題、宿題で1課題実施するような感じです。
このオリジナル課題の量が、日建学院と比較すると圧倒的に多い気がしました。
当時、日建学院オリジナル課題が3つと過去課題3年分の計6課題でした。
課題の読取り方や作図手順がしっかりしている
建築士の設計製図講座と同様に課題文の読取り方やマークの色分け、作図手順がしっかり決まっています。
初めて設備図面を描く人も抵抗なく書けるようになれると思います。
また、作図練習帳が配布されるため、空調機廻りのダクト図などを描く練習ができるのも魅力です。
総合資格学院の建築設備士講座
総合資格学院の建築設備士講座には、学科+製図、学科のみ、製図のみの3種類の講座があります。
総合資格学院の各種一級建築士設計製図講座は総合資格学院のHPをご確認ください。
学科+製図
学科のみ
製図のみ
私はその中で、建築設備士学科合格対策プランを選びました。
このプランを選んだ理由は以下の通りです。
私と同じようなタイプの方は長期を選ぶことをおすすめします。
・実務で図面を描くことがないので、設計製図試験対策は受けたい。
・費用が安かった。
学科試験の勉強方法
学科試験の概要
学科試験は、「建築一般知識」、「建築法規」、「建築設備」の3科目で構成されます。
試験時間は、「建築一般知識」と「建築法規」で2時間30分、「建築設備」で3時間30分です。
合格基準点は、建築一般知識13点(27問)、建築法規9点(18問)、建築設備30点(60問)で、総得点70点(105問)となっています。
各科目の勉強方法
基本的には、過去問をひたすら解いて、解説をしっかり読むことが大切になります。
建築一般知識
建築一般知識は、計画・環境工学・構造・施工等で構成されています。
レベル的には、二級建築士と同レベルです。
幅広い分野から出題されるので、過去問を解くときは、分野ごとで取り組むようにし、各分野で取りこぼしがないようにしましょう。
建築法規
建築法規は、建築基準法、消防法、電気事業法等で構成されます。
特に、建築基準法は、建築設備に係る分野が細かく問われます。
法令集から、適切な条文を引けるようになることも重要ですが、建築一般知識と併せて試験を行うため、時間が足りなくなる可能性があります。
時間内に解き終わるようになるべく法令集を引かないで、問題を解く力も必要になります。
過去問を解くときも、なるべく法令集を引かないで解くようにしましょう。
建築設備
建築設備は、空調、給排水、電気の各設備分野の基本的な内容から応用的な内容、最新の技術が出題されます。分野によって、得意不得意が発生すると思われるので、建築一般知識と同様に過去問を解くときは、分野ごとで取り組むようにしましょう。
設計製図試験の勉強方法
設計製図試験の概要
 設計製図試験は、「要点記述」、「選択作図(空調・給排水・電気)」、「共通作図(空調・給排水・電気)」で構成されます。
設計製図試験は、「要点記述」、「選択作図(空調・給排水・電気)」、「共通作図(空調・給排水・電気)」で構成されます。
試験時間は、5時間30分と長丁場になり、この時間内で与えられた課題の建物の設備図面や要点記述を完成させます。
4段階の評価基準があり、上位から評価A、評価B、評価C、評価Dになります。
評価Aが合格になります。
各分野の勉強方法
要点記述
毎年11個程度の要点記述が出題されます。
要点記述は問題が無限に作れてしまうため、対策が立てにくいですが、課題で出題された要点記述は、ノートやルーズリーフなどに記載しておき、隙間時間でそれを見返して勉強できるようにしておくといいです。
建築設備士の設計製図試験では、要点記述の内容が合否に直結する可能性が高いです。
課題で出題された要点記述を何回も反復して覚えるようにしましょう。
また、作図問題をこなしてくると各設備機器の仕組みが理解できるようになってくるので、作図とうまく連動させて勉強することがおすすめです。
選択作図(空調・給排水・電気)
選択作図は、空調・給排水・電気の中から1つ選択して、作図と計算問題を解きます。
空調は熱源配管図やダクト図、給排水は給排水系統図、電気は単線結線図等が出題されます。
受験生の中では、給排水を選択する人が一番多いようですが、自分の得意な分野を選択して問題ないです。
ちなみに、私は空調を選択しました。
空調を選択した理由は、給排水と電気と比較して作図量が少ないことと、計算問題も比較的簡単であったためです。
作図問題は、総合資格学院のパーツ練習帳を使って、ヘッダーや冷却塔廻り等の作図練習をしました。
計算問題は、要点記述と同様にノートやルーズリーフに課題で出題された公式を記載し、公式を覚えるようにしましょう。
共通作図
共通作図は、空調・給排水・電気の各平面図を作成します。
空調はダクト平面図や冷温水配管平面図、給排水は給排水配管平面図、電気は機器平面図を作成します。
特に、給排水配管平面図が難しいので、早々に書けるように練習をしましょう。
給排水配管平面図は、トイレや厨房、浴室等色々な用途が出題されますので、どんな用途が出題されても、描けるようにしたほうがいいです。
総合資格学院のパーツ練習帳を使って、共通作図も練習ができるのでたくさん練習をしましょう。
合格への近道
他資格との並行学習を行う
一級建築士の時は、他資格との並行学習をしないと記載したのでこれは意外かもしれませんが、建築設備士の学科試験では、建築の一般的なことから設備
他資格と内容が重複することが多い為、他資格との並行学習をお勧めします。
私は、1級電気工事施工管理技士と一級建築士の勉強を並行して行っていました。
並行学習するお勧めの資格は下記の通りです。
1級管工事施工管理技士
建築設備の空調・給排水部分が重複。
1級電気工事施工管理技士
建築法規の電気事業法、建築設備の電気部分が重複。
1級建築施工管理技士
建築一般知識全般と建築法規の建築基準法が重複。
消防設備士
建築法規の消防法、建築設備の消防設備が重複。

これらの、資格取得後に勉強を開始したり、同年度に受験予定を立てて、並行学習することで、高い相乗効果が得られます。
ただ、すべての資格を並行して受けようとすると効率が下がるため、苦手分野と関連する資格を受けるようにしましょう。
勉強スケジュール
 学科試験が6月4週目に行われるので、4月から勉強を開始するようにしましょう。
学科試験が6月4週目に行われるので、4月から勉強を開始するようにしましょう。
私の当時のスケジュールはこんな感じでした。
平日
5時 起床
5時~6時 朝食、準備
6時~7時30分 勉強(自宅)、出発
9時~12時 仕事
12時~12時30分 昼食
12時30分~13時 勉強(職場)
13時~17時30分 仕事
18時30分 帰宅
18時30分~20時 夕食、風呂
20時~22時 勉強(学校)
22時 就寝
合計 4時間の勉強時間
休日
7時 起床
7時~8時 朝食、準備
8時~12時 勉強(学校)
合計 4時間の勉強時間
できるだけ1週間で約30時間の勉強時間を確保できるようにしましょう。
まとめ
ここまで読んでいただきありがとうございました。
今回は建築設備士の合格体験記を書きました。
合格してから3年以上経過しているため、一部曖昧な表現になってしまってるところも多いかと思いますがご容赦ください。
私が所有している資格の中で、実務に一番役立っているのが建築設備士です。
勉強したことで、建築設備の図面を読むことへの抵抗がかなりなくなりました。
ビル管理会社で働いている方には、とてもおすすめな資格です。
このブログを読んでくださった皆さんが試験に合格することを祈ってます。